こんにちは、ちえです。
秋になると街がオレンジや黒の装飾で彩られ、かぼちゃや仮装を楽しむハロウィン。
大人も子どもも楽しめるイベントですが、「ハロウィンってどんな意味があるの?」「どうしてかぼちゃなの?」と子どもに聞かれて、答えに困った経験はありませんか?
今回のリサーチでは、子どもにわかりやすくハロウィンの意味や由来を説明する方法を紹介します。
家庭や学校、保育園などでの会話に役立ててください。
ハロウィンとは何の日?
ハロウィンは、毎年10月31日に行われるお祭りです。
もともとはヨーロッパの古代ケルト人の「サウィン祭」という行事が起源とされています。
この日は秋の終わりであり、冬の始まりの日。
人々は「亡くなった人の霊が戻ってくる」と信じていました。
◆子どもに説明するなら、こう言うとわかりやすいでしょう。
→「ハロウィンは“秋のおわりと冬のはじまりをお祝いする日”で、昔の人は“ご先祖さまの霊が帰ってくる日”だと考えていたんだよ」
日本でいうとお盆に少し似ている、と例えると子どもにもイメージしやすくなります。
なぜ仮装するの?
ハロウィンといえば、魔女やおばけの仮装が定番です。
これは昔の人が「悪い霊にとりつかれないように、自分もおばけのふりをしてごまかそう」と考えたことが始まりです。
◆子どもに伝えるなら、こう表現するといいでしょう。
→「本物のおばけにびっくりされないように、自分もおばけの格好をして仲間のふりをしたんだよ」
楽しく仮装する文化は、怖い霊を追い払うための知恵から生まれたんですね。
かぼちゃ(ジャック・オー・ランタン)の意味
ハロウィンの飾りといえば、顔をくりぬいたかぼちゃ「ジャック・オー・ランタン」。
これはアイルランドの伝説に由来しています。
もともとはカブを使っていましたが、アメリカに伝わったときにたくさん収穫できるかぼちゃで作られるようになりました。
光を入れたかぼちゃは、悪い霊を追い払う役割を持っています。
◆子どもに説明するなら、こう言えます。
→「かぼちゃのランタンは、おばけをこわがらせて追い払う“魔よけ”なんだよ」
「トリック・オア・トリート」の意味
子どもたちが楽しみにしているのが「トリック・オア・トリート」。
直訳すると「いたずらか、お菓子か」という意味です。
もともとはヨーロッパで、貧しい人々が家々を回って食べ物をもらい、そのお礼に亡くなった人のために祈った習慣が由来です。
それがアメリカで「お菓子をもらう遊び」に変わり、今の形になりました。
◆子どもにわかりやすく言うと、
→「“トリック・オア・トリート”は“おかしをくれなきゃいたずらするぞ”っていう合言葉だよ」
日本では遊び感覚で楽しむことが多いですが、もともとは祈りや感謝の気持ちが込められた習慣だったのです。
日本でのハロウィンの広まり

日本でハロウィンが知られるようになったのは1980年代。
ディズニーランドのイベントやテーマパークの影響で広がり、2000年代には仮装イベントやパレードが全国的に人気になりました。
今では子どもが楽しむ行事として保育園や学校でも取り入れられることが増えています。
子どもに説明するときの工夫
ハロウィンの意味や由来を子どもに話すときは、ただ歴史を説明するだけでは難しいので、次のような工夫をしてみましょう。
1. 日本の行事と比べる
→ 「ハロウィンはお盆みたいなものだよ」と例える。
2. 絵本やイラストを使う
→ かぼちゃのランタンやおばけの絵を見せながら話すとイメージしやすい。
3. 物語形式で伝える
→ 「昔の人はね、夜におばけがやってくると思ってたんだって」とストーリー風に話す。
4. 一緒に体験する
→ かぼちゃを飾ったり仮装したりすることで、自然に意味を学べる。
子どもにわかる!ハロウィンの意味や由来と伝え方ガイド|まとめ
ハロウィンはただ仮装やお菓子を楽しむ日ではなく、古代ケルト人の行事がもとになった「霊を迎える日」でした。
* 仮装は悪い霊から身を守るため
* かぼちゃのランタンは魔よけ
* 「トリック・オア・トリート」は感謝と祈りが起源
子どもに説明するときは、「おばけのふりをして悪い霊から守った」「かぼちゃは魔よけ」といったシンプルな言葉で伝えると理解しやすいです。
家族で楽しく飾り付けや仮装をしながら、ハロウィンの本当の意味を一緒に感じてみてください。

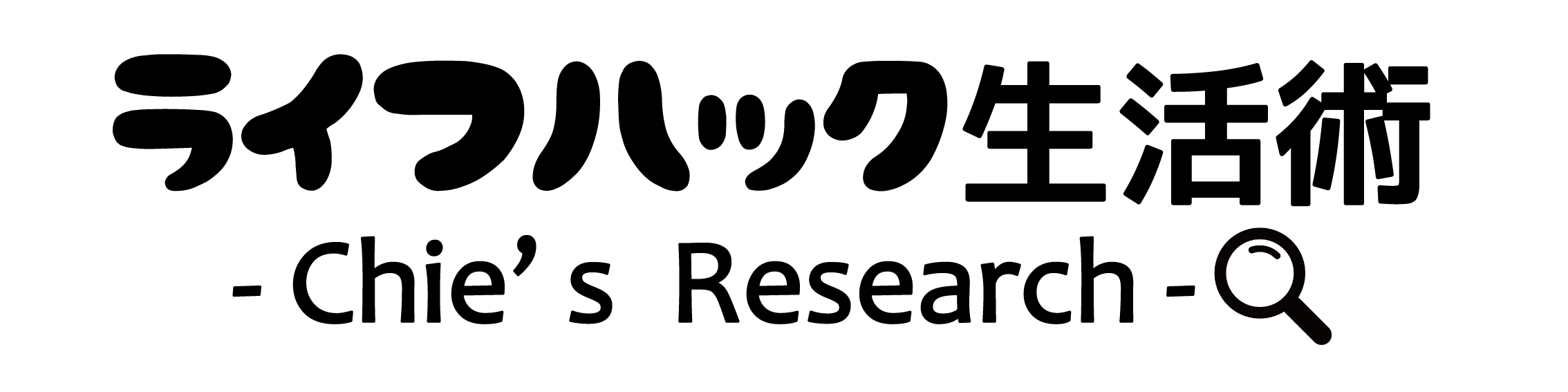




コメント