こんにちは、ちえです。
お盆が近づくと、「墓参りっていつ行くのが正しいの?」「霊供膳(れいくぜん)は何日間お供えすればいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
地域の風習や家庭によって少しずつ違いがあるため、はっきりと決まったルールがあるわけではありませんが、一般的な目安はあります。
今回のリサーチでは「お盆 墓参り いつからいつまで」「お盆 霊供膳 いつからいつまで」といった疑問に、わかりやすくお答えしていきます。
1. お盆の基本:いつからいつまで?

まずは、お盆の日程について簡単におさらいしておきましょう。
一般的なお盆の日程
多くの地域では、8月13日〜16日が「お盆」とされています(旧盆)。
● 8月13日:迎え盆(ご先祖様を迎える日)
● 8月14日〜15日:中日(ご先祖様と過ごす日)
● 8月16日:送り盆(ご先祖様を送り出す日)
ただし、東京など一部地域では7月13日〜16日に行う「新盆(新暦盆)」が一般的です。ご自身の地域の風習を確認しておくと安心ですね。
2. 墓参りはいつ行くのが正解?

お盆の墓参りは、ご先祖様の霊を迎える、あるいは送る大切な行事。では、いつ行くのが良いのでしょうか?
墓参りの一般的なタイミング
“迎え盆の前日か当日(8月12日〜13日)”に行うのが一般的です。
これは、「きれいに整えたお墓でご先祖様をお迎えする」という意味があります。墓石を磨き、お花を供え、線香を手向けて、気持ちよくお迎えできる準備をしましょう。
中日や送り盆に行く場合も
14日・15日・16日に墓参りする方も多いです。
特に親戚や家族が揃う日を選ぶことが多く、都合に合わせて調整して問題ありません。
墓参りのマナー
● 墓石の掃除はたわしや布でやさしく
● 枯れた花やゴミは持ち帰る
● 線香は風向きに注意して安全に
特別な形式があるわけではありませんが、心を込めてお参りすることが大切です。
3. 霊供膳とは?いつからいつまでお供えするの?

霊供膳とは?
「霊供膳(れいくぜん)」とは、ご先祖様のために供える精進料理のお膳のことです。
仏壇にお供えする料理で、肉や魚を使わず、五菜(ごさい)と呼ばれる小鉢が一般的です。
構成例:
● ごはん
● 煮物(昆布・里芋など)
● おひたし(ほうれん草・小松菜など)
● 香の物(漬物)
● 汁物(味噌汁など)
このお膳は、ご先祖様への感謝を形にしたもの。派手でなくても、できる範囲で心を込めて準備しましょう。
お供えする期間はいつからいつまで?
霊供膳の供え始めと終わりについても地域差はありますが、一般的には以下の通りです。
● 8月13日(迎え盆)から8月16日(送り盆)までの4日間
● 毎日、新しい料理をお供えするのが理想とされています。
ただし、忙しい場合や高齢のご家族がいらっしゃる場合などは、無理のない範囲でお供えする日を選んでも大丈夫です。
お供えのタイミングと片づけ
● 朝や昼前にお供えするのが一般的です。
● 食事が終わったと想定し、30分〜1時間ほどで下げるのが良いとされています。
● 下げたお膳は家族でいただくと、「ご先祖様と食事を共にした」とされ、縁起が良いとされています。
4. 霊供膳は毎日作らなきゃダメ?
「毎日違うものを用意するのは大変…」と感じる方も多いですよね。
大丈夫、完璧を目指さなくても問題ありません。
無理せず、できる範囲で
● 同じ献立を繰り返してもOK
● ご飯や味噌汁だけの日があってもOK
● 市販の惣菜を活用するのもアリ
大切なのは、「ご先祖様に感謝の気持ちを伝える」ことです。形式より、気持ちを込めてお供えすることを大切にしましょう。
5. 地域の風習や家庭の考えを尊重して

お盆の過ごし方は、地域によっても、家ごとにもさまざま。親戚や年長者に相談して、家族のやり方を大切にしていきましょう。
例えば…
● 「うちは15日に墓参りをするのが恒例」
● 「霊供膳は13日と16日だけでいいよ」
といったケースもよくあります。決まりすぎていない分、柔軟に対応できるのが日本のお盆の良さでもありますね。
まとめ:お盆は心をこめて過ごす期間
お盆は、ご先祖様とつながる大切な時間。
墓参りも霊供膳も、「こうしなきゃいけない」というよりは、「心をこめて行うこと」が一番大事です。
● 墓参りは12日〜13日ごろがおすすめ(でも都合がつけばいつでもOK)
● 霊供膳は13日〜16日まで、毎日が理想だけど、無理しなくて大丈夫
● 地域や家庭のルールに合わせて気楽に取り組んで
慌ただしくなりがちなお盆ですが、ほんの少しの準備と優しい気持ちで、ご先祖様に「ありがとう」と伝えられる時間になりますように。

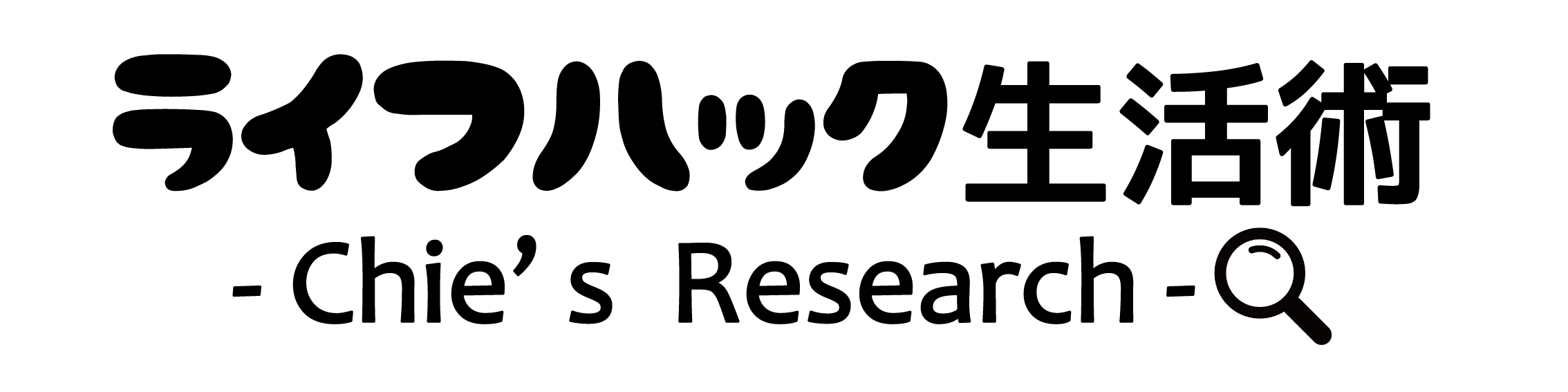



コメント