こんにちは、ちえです。
七五三は子どもの健やかな成長を祝う大切な行事。
晴れ着を身にまとった姿を見られるのは、親にとっても嬉しい瞬間です。
ですが、「着付けを美容院にお願いすると費用もかかるし、時間の予約も大変…」と感じる方も少なくありません。
そこで注目されるのが「七五三の子供の着付けをママ自ら」挑戦する方法です。
今回のリサーチでは、初心者の主婦でも取り組みやすい七五三の着付けポイントや準備、コツをご紹介します。
七五三の着付け、自分でできるの?
「七五三の着付けは難しそう」と思われがちですが、実際には子ども用の着物は大人ほど複雑ではありません。
特に最近は簡易帯やワンタッチ帯が増えており、手順を押さえれば自宅でもきれいに着付けることが可能です。
自分で着付けをするメリットには以下のような点があります。
● 費用を節約できる
美容院や着付けサービスは1人あたり5,000〜10,000円ほどかかる場合も。兄弟姉妹がいればさらに出費が増えます。
● 時間に余裕が持てる
支度にかかる時間を自宅で調整でき、写真館や神社への移動もスムーズ。
● 思い出になる
ママが手ずから着せてあげる体験そのものが、子どもにとって特別な思い出になります。
|
|
七五三の着物種類と着付けの基本
子どもの年齢や性別によって、着物の形や必要な小物が少しずつ違います。
3歳(女の子)
● 着物(肩上げ・腰上げ済みのもの)
● 被布(ひふ)
● 長襦袢
● 足袋
● 草履
3歳の女の子は帯を結ばず、被布を羽織るスタイルが一般的。着付けも簡単で初心者向けです。
5歳(男の子)
● 羽織
● 着物
● 袴
● 長襦袢
● 角帯
● 草履
男の子は袴の着付けがポイント。腰ひもの扱いに慣れればスムーズに仕上がります。
7歳(女の子)
● 着物
● 長襦袢
● 帯(作り帯または結び帯)
● 帯揚げ・帯締め
● 足袋・草履
7歳の女の子は大人の着付けに近づきますが、最近は作り帯が多いため比較的簡単に結べます。
七五三の着付けに必要な道具
着物や帯だけでなく、着付け用の小物も揃えておくと安心です。
● 腰ひも(3〜4本)
● 伊達締め(1〜2本)
● 帯板
● タオル(体型補整用)
● コーリンベルト(着崩れ防止)
セットで販売されている「子ども着付け小物セット」を利用すると揃えやすいです。
|
|
自分でできる!着付けの手順
ここでは一例として、7歳の女の子の着付け手順をご紹介します。
1. 肌着・足袋を履かせる
動きやすい状態にしておく。先に足袋を履かせると後で楽です。
2. 長襦袢を着せる
衿を抜いて首元にゆとりを持たせ、腰ひもで固定。
3. 着物を羽織らせる
丈を調整し、腰ひもで固定。胸元は左右が重なりすぎないように整える。
4. 帯を結ぶ(作り帯がおすすめ)
背中に差し込むタイプなら、初心者でも10分ほどで完成。
5. 帯揚げ・帯締めを整える
帯がずれないよう固定しながら見た目も華やかに。
6. 仕上げに羽織や被布を着せる(3歳や5歳の場合)
被布は羽織るだけで完成、男の子の羽織は紐で結びます。
着付けのコツと注意点
● 着崩れ防止には腰ひもをしっかり
苦しくない程度にきつめに締めるのがポイント。
● 体型補整はタオルで簡単に
ウエストや胸元にタオルを入れると帯が安定。
● 子どもが飽きないように工夫
着付けは10〜15分以内を目指しましょう。先にトイレを済ませておくのも大切。
● 写真映えを意識
衿元のバランス、帯の高さを整えるだけで見栄えが変わります。
事前に練習して安心
いきなり当日挑戦するのは不安…という方は、事前に一度練習しておきましょう。YouTubeなどに「七五三 着付け 自分で」の動画がたくさんあるので、視覚的に手順を確認すると理解しやすいです。
また、写真館で前撮りをしておけば、当日の着付けに失敗しても安心。
自分でできない時の工夫
● 作り帯・ワンタッチ袴を利用する
● 被布スタイルを選ぶ(特に3歳はこれで十分華やか)
● ママ友や家族に手伝ってもらう
どうしても難しい場合は、美容院や出張着付けサービスを利用するのも手。
事前に「部分的に手伝ってほしい」と伝えるのもOKです。
|
|
七五三着付け自分でできる?まとめ
七五三の着付けは「自分で」挑戦することで、節約にもなり、親子にとって特別な思い出作りにもつながります。
最初は難しく感じるかもしれませんが、作り帯や被布スタイルを取り入れれば初心者でも十分対応可能です。
七五三のとき子供の着付けを自分で実践するためには、
● 必要な小物を揃える
● 子どもの年齢や性別に合った着物を選ぶ
● 事前に練習して当日はスムーズに
がポイント。
お子さまの大切な記念日を、ママの手で彩ってあげてください。

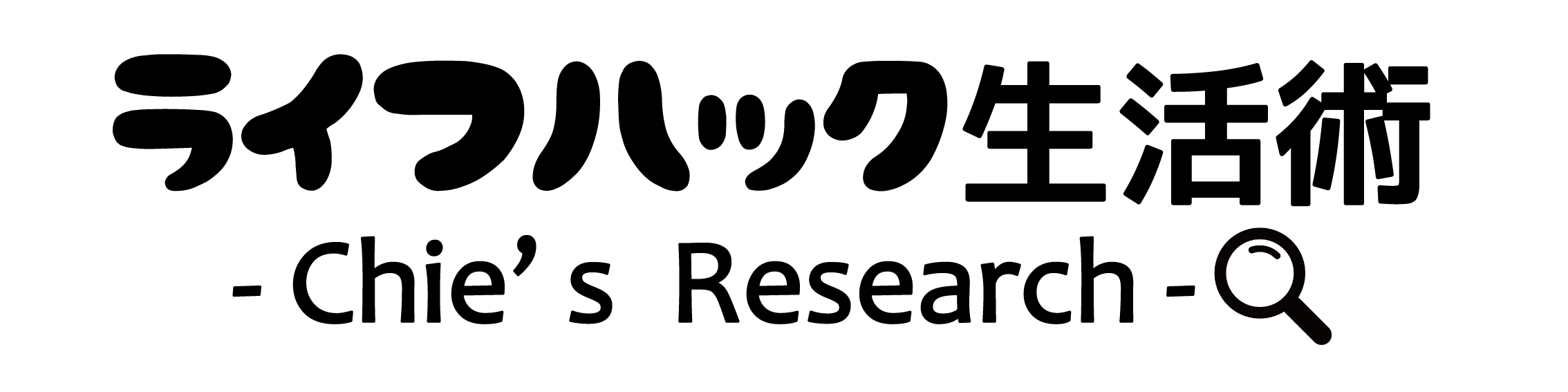







コメント